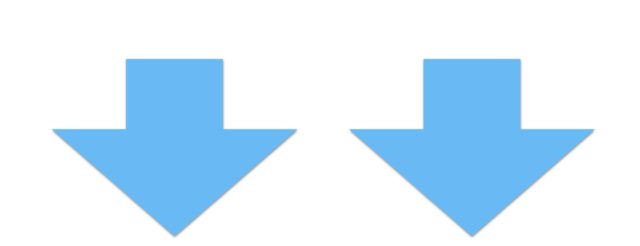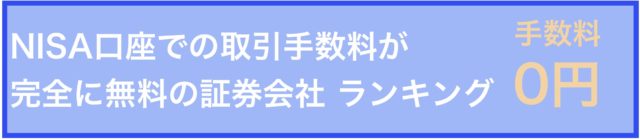STEP 1では、株式投資に『必要なもの』と、『必要な知識』を知っていただきます。
『必要なもの』は次の2つになります。
・投資資金 ⇒ 株を買うお金を用意する
株式投資を始めるには、『証券口座』と『投資資金(元手)』が必要です。これらについての説明をします。その説明を参考にして、どこの証券口座を開設するのか、投資資金(元手)をいくらにするのかを決めていきましょう。具体的な口座開設方法については、STEP 2で解説します。
さらに、『必要な知識』は以下の6つになります。
・投資する株(銘柄)を探す方法
・株(銘柄)の分析方法
・取引のルールを覚える
・資金管理をする
・税金について知る
こちらは、STEP 1では、『株の仕組み』だけをお伝えします。他の5つは、今は「このような知識が必要なんだな」と、知るだけで大丈夫です。今後のステップで、実践しながら覚えていきましょう!
それでは、まずは株式投資に必要なものひとつめの『証券口座』についてお伝えしていきます。
株の売買に必要な『証券口座』とは
株の売買をするためには、証券会社の口座を開設する必要があります。
なぜなら、株は『証券取引所』で売買されていて、そこに注文を出すことが、証券会社の役割だからです。あなたは、証券会社に口座を開いて、そこにお金を預けることにより、株の注文が出せるようになります。
例えば、トヨタの株を《100株6,700円》で買いたいAさんと、《100株6,700円》で売りたいBさんがいたとします。(AさんはGMOクリック証券の口座を持っていて、BさんはSBI証券の口座を持っています)
以下の図のとおりです。

この2人の注文が証券会社を通じて、『証券取引所』に並びます。
この2人の注文は同じ銘柄(株の名称)で、同じ値段のため、値段の折り合いが付いた状態になりました。そのため、2人の注文は成立します。
このことにより、トヨタの株を買いたいAさんはトヨタの株を100株手に入れて、トヨタの株を売りたいBさんは現金(6,700円×100株=)670,000円を手に入れたわけです。
図で表すと下記のとおりです。

このように、株を取引する場所が『証券取引所』で、株の注文を出すところが、『証券会社』になります。その証券会社に口座を持ち、お金を預け入れることで、あなたは株の注文を出せるようになります。ですから、まずは証券会社を選んで口座を開設していきましょう!
証券会社の選び方
証券会社に口座を開設するために、まずは証券会社選びからスタートします。
証券会社は日本全国で1,000社以上あるため、株式投資初心者のあなたは、どこの証券会社にしたら良いのか迷う人もいるはずです。
証券会社の選び方は『あなたの投資スタイル』に合う証券会社を選ぶと良いでしょう。
それぞれの証券会社にはサービスに特徴があります。そこで、あなたの投資スタイルに合うサービスを提供している証券会社を選ぶと良いわけです。
投資スタイルとは、以下のようなことで、お金を株式投資でどのように増やすかのことです。
さまざまな投資スタイル
| 長期投資 | 割安株 | 成長株 | 安定株 |
|---|---|---|---|
| 短期投資 | デイトレード | スイングトレード | 逆張り、順張り |
| 海外株式 | アメリカ株 | 中国株 | 韓国株 |
| 投資信託 | 国際株式型 | 国内株式型 | 国際債券型 |
| 積立式 | 投信積立 | 積立NISA | るいとう |
ここでは、さまざまな投資スタイルについて、詳しくは説明いたしません。
当サイトでは、株の長期投資をオススメしています。株価が割安で成長している企業を見つけて、その企業の株を長い間保有する投資スタイルになります。
長期投資のスタイルで証券会社を選ぶとすると、企業の業績を分析するツールや、長期投資に合う株を見つけるためのツールが揃っている証券会社の口座を開くと便利です。
このように、投資スタイルによって、証券会社を選びましょう。
証券会社の種類
証券会社を大まかに分けると、全国に店舗を構えている『総合証券』と、ネット取引中心の『ネット証券』に分かれます。以下の図のとおりです。

証券会社は、ネット証券だけでも数多くあり、それぞれ異なったサービスを提供しています。
例えば、『A証券は海外の株を多く取り扱っている』『B証券は投資信託の種類を多く取り扱っている』さらに『C証券は株の取引手数料が格段に安い』という具合です。

インターネットを通じて、このページをご覧になっているあなたは、ネットを使いこなせているはずです。そのため、証券会社はネット証券から選ぶことをオススメします。
なぜなら、総合証券と比べるとネット証券の方が、株の取引をするための手数料が安いのです。
下記の表は、私が開設している証券口座の株の取引手数料です。野村證券が全国に店舗を構えている総合証券になります。
私が開設したことのある証券口座(口座開設した順番どおり)
| 取引金額 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜50万円 | 〜100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村證券 | 150円 | 324円 | 515円 | 1,029円 | |
| マネックス証券 | 100円 | 250円 | 450円 | 成行1,000円 指値1,500円 |
|
| 岩井コスモ証券 | 86円 | 259円 | 432円 | 864円 | |
| GMOクリック証券 | 95円 | 105円 | 260円 | 470円 |
※岩井コスモ証券は、月額で定額制(月に10,800円以上はかからない料金設定)もあります。
ご覧のとおり、一番手数料の安い証券会社と総合証券である野村證券の手数料を比べると、倍近い手数料の差があります。
株を長期保有するのなら、手数料の差はそれほど気にする必要はありませんが、手数料が安いに越したことはありません。株の取引手数料で証券口座を選ぶのなら、ネット証券が良いでしょう。
株の取引手数料の他、証券会社を選ぶ際のポイントは主に以下の4つになります。
2.ツールの性能や使いやすさ
3.投資のための情報量
4.取り扱い商品の種類の違い
手数料やその他サービスの違いを比較した、証券会社の選び方については、こちらの記事を参考にしてください。
↓ ↓ ↓ ↓
私が使っているネット証券の中では、クリック証券とマネックス証券をオススメします。
詳しいことは、上記の記事に書いてあります。主に手数料が安いことと、投資に役立つツールに便利なツールがあり、さらに使い勝手も良いことから、こちらを利用しています。
使い勝手は、人により好みもありますので、まずは、いくつかの証券会社の口座を開設してみて使ってみることをオススメします。
特に海外の株や投資信託(投資のプロが運用するもの)やIPO(新規公開株)などに興味のない方は、取引手数料が業界最安値水準の『クリック証券』で良いですし、海外の株や投資信託やIPOにも興味がある方は、『マネックス証券』や『SBI証券』で良いでしょう。
証券口座の開設方法については、STEP 2で詳しく解説していきます。
証券会社を決めたら、次は『口座の種類』について、知っておく必要があります。
口座の種類について知り『一般口座』か『特定口座』を選ぶ
証券口座を開設する前に、『口座の種類』について知っておきましょう。なぜなら、口座の種類は3つあり、その口座の種類により、株の取引で得た利益に対する『税金の納め方』や『納める金額』が異なります。そのため、あらかじめ口座の種類を決める必要があるのです。
口座の種類は、次の3つになります。
2.特定口座(源泉徴収あり、源泉徴収なし)
上記の『一般口座』と『特定口座』は、普通の口座で、NISA口座は少し特殊な口座になります。そのため、分けてみました。
『NISA口座』は、一定の条件の範囲で株の取引をすると、株の取引に対する税金(税率20.315%)を納める必要がなくなる口座です。NISA口座は開いても開かなくても構いません。しかし、『一般口座』か『特定口座』は開く必要があり、口座開設をするときに選びます。
ですから、まずは『一般口座』と『特定口座の源泉徴収あり』『特定口座の源泉徴収なし』の中から、口座の種類を選ぶことが、口座選びのポイントになります。
その後、必要に応じて、NISA口座を開設するのかしないのかを考えると良いでしょう。(NISA口座については後で簡単な説明をします。)
証券口座の種類はこの3つから選ぶ!
特定口座の源泉徴収あり
特定口座の源泉徴収なし
3つの口座の違いとは?
『一般口座』『特定口座(源泉徴収あり)』『特定口座(源泉徴収なし)』こちら、3つの口座の違いは、主に以下の2つです。
2.『税金の納め方』
表にまとめると、次のとおりです。
| 一般口座 | 特定口座
(源泉徴収あり) |
特定口座
(源泉徴収なし) |
|
|---|---|---|---|
| 年間取引報告書 | 自分で作成 | 証券会社が作成 | 証券会社が作成 |
| 税金の納め方 | 自分で確定申告をして納める | 証券会社が天引きして納める | 自分で確定申告をして納める |
こちら、『年間取引報告書の作成方法』と『税金の納め方』2つの違いを説明します。
1.年間取引報告書の作成方法
1つ目の違いは、株の年間取引報告を自分で作成するか、証券会社が作成してくれるかの違いになります。
年間取引報告書は、株の年間の取引を記載する書類です。これは税金を払うために必要な書類になります。以下の見本のようなものです。

こちらは、私が祝いコスモ証券を利用していた時に送られてきた見本です。(年間取引報告書は税務署に提出しているため、本物は残っておりません)
特定口座で株の取引をすると、上記のような年間取引報告書を、1年間の株の取引が終わったところで、証券会社が作成してくれます。一般口座で取引する場合は、自分で作成する必要があります。
2.税金の納め方
2つ目の『税金の納め方』の違いは、株の取引に対する税金を、1年間の取引がすべて終わった後に、自分で確定申告をして納めるのか、株の取引ごとに源泉徴収されるかの違いになります。
『源泉徴収』とは、株の利益が確定したとき(株を売るため現金が口座に入る)に、そこから天引きされて証券会社経由で税金を納めることです。
例えば、30万円の株を50万円になったときに売ると、株の利益は20万円になります。
計算式 50万円(売値)-30万円(買値)=20万円(利益)
20万円の株の利益に対する税金は40,630円(税率20.315%)になります。そこで、20万円の利益の中から、この40,630円が引かれます。
つまり、株を売って得たお金50万円は、税金40,630円を天引きされて、『特定口座』に戻ってくるわけです。
計算式 500,000(売値)ー40,630(税金)=459,370
図であらわすと、下記のとおりです。

このように、『源泉徴収あり』の口座で取引をすると、株を売るたびに、利益にかかる税金が証券会社の口座から源泉徴収されます。
その後、株の取引で損失が出た時には、引かれた税金が戻ってきます。
一方『一般口座』や、『特定口座(源泉徴収なし)』の場合は、あなたが自分で確定申告をして、税金を銀行などの金融機関へ払い込みに行く必要があります。
口座の種類について、詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
↓ ↓ ↓ ↓
以上のように、『年間取引報告書の作成』と、『税金の納め方』の違いが、3つの口座開設選びのポイントになります。
株式投資初心者にオススメなのは『特定口座の源泉徴収あり』
株式投資初心者にオススメな口座は『特定口座の源泉徴収あり』になります。
年間取引報告書の作成や確定申告は面倒な作業です。『特定口座の源泉徴収あり』を選ぶと、その面倒な作業を一切する必要はありません。
先述のとおり、年間取引報告書は、証券会社が用意してくれますし、税金は利益が出るたびに、口座から差し引かれます。そのため、自分で確定申告の書類を作成したり、税金の払い込みに行かなくて済むわけです。
そのことから、株式投資初心者にオススメな口座は『特定口座の源泉徴収あり』になります。
NISA口座は開設するべきか
先述のとおり、NISAの口座は開いても開かなくても構いません。NISA口座で取引をすると、税金はかかりませんし、確定申告の必要もありません。そのため、かなりお得な感じもします。
しかし、NISA口座には一定の条件やデメリットがあります。それにより、必ずしも、NISA口座を開いた方が良いとは限りません。
その辺りのNISA口座の特徴やメリット、デメリットをお伝えします。そこをふまえて、NISA口座を開設するのかを決めましょう。
NISA口座については、下記の記事で詳しくお伝えしています。そちらもご覧ください。
⇒ 『株や投資信託の利益や配当金に税金がかからないNISA口座について知る』
こちらでは、簡単にNISA口座の特徴や『メリット、デメリット』をお伝えしていきます。
NISA口座の特徴は年間120万円までの投資で得た利益に対する税金が非課税になる
NISAとは、少額投資非課税制度のことで、年間120万円までの株や投資信託の投資で得た利益が、非課税になる制度のことです。株をNISA口座で買うことで、最長で5年間まで保有でき、その5年以内に売った場合の利益が非課税になります。
もし、普通の口座(一般口座、特定口座)で株の売買をして利益が出た場合、その得た利益に対して、20.315%の税金を納めることになります。
例えば、100万円(投資額120万円以内)の株を買い120万円で売ったとします。その場合、利益は20万円になります。
計算式 120万(売値)−100万(買値)=20万円(利益)
普通の口座で取引をした場合、その20万円の利益に20.315%の税金がかかります。つまり、納める税金は、40,630円になります。
計算式 200,000×0.20315=40,630円
しかし、NISA口座で先ほどの株の売買をすると、この40,630円(株で得た利益20万円に対する税金)は納める必要がありません。よって、その分お得になるわけです。
NISA口座のデメリット
税金を納めなくて済むことから、一見お得なNISA口座も、デメリットはあります。NISA口座を利用する場合、しっかりとそのデメリットを把握して利用することが望ましいといえます。
NISA口座のデメリットは、主に次の2つになります。
2.損失繰越が出来ない
NISA口座での株の売買は非課税のため、確定申告の必要はありません。その確定申告をしないために、株の取引の『損益通算』と『損失繰越』が出来ないことはデメリットになります。こちらの2つを説明します。
1.損益通算が出来ない
NISA口座のデメリットの1つ目は、『他の証券口座』の株取引と損益通算が出来ないことです。
損益通算とは、株を売買すると利益ばかりではなく、損失も出ます。その『利益』と『損失』を合わせることです。
普通の口座であれば、一方の証券口座の株取引で利益を出したとしても、他の証券口座の株取引で損失を出した場合、損益通算をすることで、納める税金を減らせます。しかし、NISA口座の場合は、この損益通算が出来ません。そのため、税金を余分に払ってしまう可能性があるわけです。
例えば、次のようなことです。
特定口座同士の損益通算
まずは、普通の口座(特定口座)同士の場合を説明します。クリック証券、マネックス証券共に、普通の口座の特定口座です。
マネックス証券(特定口座) 年間損失 20万円
上記のように、クリック証券の特定口座では、年間の利益が20万円出ました。しかし、マネックス証券の特定口座では20万円の損失がでています。この場合、クリック証券の『利益20万円』とマネックス証券の『損失20万円』を損益通算することにより、株の年間損益は0円になります。
つまり、税金を納める必要はありません。
これがもし、損失を出した方のマネックス証券が、NISA口座だとします。以下のような場合です。
マネックス証券(NISA口座) 年間損失 20万円
この場合、クリック証券の特定口座と、マネックス証券のNISA口座は損益通算が出来ません。そのため、株の年間損益は、クリック証券で出た利益20万円がそのままになります。
つまり利益20万円分の税金40,630円を納める必要があるわけです。
これは、証券会社が同じ場合でも起こります。次のような場合です。
クリック証券(NISA口座) 年間損失 20万円
この場合も、一方がNISA口座のため、損益通算が出来ないわけです。
つまり、年間利益20万円分の税金40,630円を、納める必要があります。
NISA口座を開設して株の取引をすると、このような損益通算ができないケースが起こります。そのため、本来は払う必要のない税金を、払わなければならなくなる可能性があるわけです。
これでは、NISA口座では損失が出て、普通の口座の利益からは税金も取られてと、踏んだり蹴ったりです。
このように、損益通算が出来ないことは、NISA口座のデメリットになります。
2.損失繰越が出来ない
NISA口座のデメリットの2つ目は、損失の繰越しが出来ないことです。
一般口座や特定口座の場合は、年間で損失が出た場合、その損失を翌年以降3年間繰り越せます。損失を翌年以降に繰り越すことで、翌年以降に株で利益を出した場合、その『利益』と『繰り越していた損失』を合算できるわけです。
先ほどの、損益通算の話と似ていますね。
例えば、以下のような場合です。
特定口座 2018年利益 80万円
特定口座を使い、2017年に株の損失が80万円出て、2018年に80万円の利益が出たとします。
この場合、2017年に損失の80万円を確定申告をして損失を繰り越します。そうすることで、2018年以降に出した利益と損益通算ができます。そのため、2018年の利益80万円は、2017年の損失80万円と損益通算できます。
2017年と2018年を損益通算すると、利益が0円になるため、2018年の利益80万円に対する税金は払う必要はありません。
ところが、NISA口座の場合、この損失の繰り越しが出来ません。そのため、次のようなことが起こります。
特定口座 2018年利益 80万円
この場合、NISA口座の2017年の損失は繰越しが出来ません。そのため、2018年は80万円の利益に対する税金162,520円を払うことになります。
このように、損失繰越が出来ないことも、NISA口座のデメリットと言えます。
NISA口座のデメリットを回避する方法はあるのか?
先述のように、NISA口座のデメリットのケースは、NISA口座で株の損失を確定させて、さらに普通の口座で利益を確定させた場合におきます。
これを踏まえて、NISA口座のデメリットを回避する方法を考えますと、以下のようなことが考えられます。
『年間投資額を120万円以下に抑えて、NISA口座のみで株の売買をする。』
年間投資額が120万円以下であれば、NISA口座のデメリットは回避できそうです。なぜなら、NISA口座の年間の投資額は上限が120万円までと決まっています。そのため、NISA口座で120万円を超える買い付けはできません。年間120万円の投資額を超える分は、普通口座で取引をすることになります。
つまり、年間の投資額が120万円以下であれば、NISA口座の中だけで株の取引を済ませられるわけです。そうすることで、NISA口座以外での利益は出ないため、余分な税金を払う必要はないわけです。
NISA口座のデメリットを回避する際の注意点は2つ
先述のとおり、NISA口座のデメリットを回避するには、NISA口座だけで取引をすることです。ただし、これには注意点が2つあります。
その注意点の2つは、以下のとおりです。
2.NISA口座は『最長5年までの保有の期限がある』
この2つについて解説します。
1.NISA口座の『年間の投資額上限は120万円』について
この年間120万円の投資額の上限は、NISA口座で保有していた株を売って、またNISA口座で株を買った場合も含まれます。
例えば、今年NISA口座で60万円の株を買って保有していたとします。その株を40万円で売ったとします。次にまた、NISA口座で60万円の株を買った場合、年間投資額は120万円になってしまいます。
このように、NISA口座の上限の投資額は、株を繰り返し売買してしまうと、すぐに使い切ってしまうわけです。
年間の取引額上限を使い切ってしまうと、使い切った後は、先述のとおり、普通の口座で株の取引をすることになります。そうなると、NISA口座のデメリットのケースが起こり得るわけです。
そこで、年間120万円の取引額を超えないようにする必要があるわけですが、それには、NISA口座で保有する株を、すぐに売らないようにしなければなりません。
そうなると、NISA口座では、すぐには売る必要のない株を買う必要があるわけです。
ここがしっかりと管理出来て、年間投資額が120万円を超えない程度の資金であれば、NISA口座のデメリットは回避できると考えても良いでしょう。
2.NISA口座は『最長5年までの保有の期限がある』こと
注意点の2つ目は、『NISA口座は最長5年までの保有の期限がある』ことです。
保有期限の5年があることから、5年後に利益が出ていなければ、一度は損失を確定することになります。そのため、いくらNISA口座で損失を出すとデメリットがあるからと、売らないでいても、5年後には一度、損失を確定させる必要があるわけです。
こればかりは、いくら気を付けていても、回避できません。なぜなら、株はいつ大きく上がって利益が出せるのかは、誰にもわからないからです。
例えば、株価の推移のケースには、次のようなケースがあります。
画像で表すと以下のとおりになります。

以上のような、3つのケースをお伝えしました。
A株のようなケースは、2007年のサブプライムローン問題からのリーマンショックを経て、2013年以降の株価回復のケースが当てはまります。
B株のようなケースは、1998年~2000年のITバブル期のIT株のようなケースが当てはまります。
また、
C株は最近(2018年12月現在)の『ライザップグループ』の株が当てはまりそうです。
このように、株価を形成するパターンは様々です。いつ上がっていつ下がるのか、またどこまで上がるのかどこまで下がるのかは、誰にもわかりません。
つまり、5年後に利益を出せているのかも、損失を出しているのかも、わからないことになります。
特に株の長期投資では、株を10年間は保有したいものです。なぜなら、しっかりと業績が良く成長している企業の株であれば、2,3年は損をしていても、10年のうちにはしっかりと株価は回復してきて、買値の何倍も上がってくるからです。
そのようなことがあるため、NISA口座の最長5年までの期限では短すぎるといえます。
これでは、NISA口座のデメリットをずっと回避することは、ほぼ不可能ではないでしょうか?
NISA口座は必要とは限らない
先述のようにNISA口座にはデメリットがあり、それを回避する方法も、なかなか難しいといえます。そのため、NISA口座はどうしても必要とは限りません。
NISA口座は先述のように繰り返し売買すると、すぐに年間投資額120万円を超えてしまいますし、株の短期売買には向いていない口座です。
つまり株の長期投資に向いている口座になりますが、最長で5年という制約があります。株の長期投資では、10年以上持つことも多いため、必ずしもNISA口座を開設して利用した方が良いとはいえないわけです。
それに、先述のとおり全てのNISA口座の取引で利益を出すのも難しいわけで、損失を出すとデメリットが生じるのでは、そこまで、NISA口座は必要ではないといえます。
以上のように、必ずしも、NISA口座は必要ではありませんが、資金が少ないうちは、長期保有することでNISA口座のメリットはあります。5年以内に利益が出れば、税金はかからないことは、メリットです。(5年後はわかりませんが)
ここでお伝えした、『メリット・デメリット』をしっかりと理解したうえで、上手にNISA口座を活用していただけたらと思います。
さて、ここまでで『証券会社』を選び、『口座の種類』の選び方もお伝えしました。これで、証券口座開設の申し込みまでは、スムーズにいけるはずです。
次は、株式投資に必要なものの2つ目である、『投資資金』についてお伝えします。
『投資資金の額はすでに決まっている』と、いう方はSTEP2の口座開設の仕方へ進んでください。
⇒ステップ2へ進む 『STEP2 [〜3日目]証券口座を開設して入金する』
株式投資の投資資金(元手)をいくらにするのか、まだ決まっていない人は、この先へお進みください。
投資資金(元手)はいくら必要か
株を始めるときに『投資資金はいくら用意した方がいいのだろうか?』と、考える人は多いです。
株を買うには資金(日本円)が必要で、その資金を証券口座に入金することで、株の注文を出せるようになります。
例えば、30万円を証券口座に入金すると、30万円以下の株を買うことができます。
10万円分の株を3社でも良いですし、10万円分の株を2社買って、後の10万円は証券口座に残しておくこともできます。
株の元手をいくらにするのかは人により異なります。あなたの株式投資の元手をいくらにしたら良いのかを考えていきましょう!
それではまず、「実際に株を買うには、いくらあれば買えるのか?」
株式投資はいくらあれば始められるのかを、お伝えしていきます。
株式投資はいくらあれば始められるか?
株を始めることは資金1万円からでも出来ますし、10万円からでも出来ます。
試しに、資金1〜10万円で買える株をスクリーニング(選別して見つける)してみます。それにより、買える株がいくつあるのかがわかります。
資金1万円では、以下のようなスクリーニングの結果が出ました。(2018年5月)
マネックス証券のスクリーニングツール(選別ツール)

資金1万円で買える株は『29社』です。
「これは少ない!!」
全部で4,000銘柄(株の名前)ある内の、29銘柄しかありません。
では、資金10万円では、どうでしょうか?

資金10万円で買える株は『1,085社』です。全体の1/4ですから、まだまだ少ないですが、それなりにあると言えます。
このように、資金1万円からでは、実際の株がほとんど買えません。そのため、現実味がないことがわかります。
また、1万円以下の株はほとんどの株がボロ株と呼ばれるものになります。そのため、投資をするには適さない株になります。
ボロ株とは?
ボロ株とは、業績が赤字で会社の財政状態もかなり悪い状態の株で、株式市場では価値がほとんどない株のことをさします。そのような状態であるため、誰にも買われないことから、株価が万年安い状態でいるわけです。
このように、投資対象としてはふさわしくない銘柄ばかりなのが、ボロ株の特徴になります。
ボロ株は時として、万年赤字状態から脱却し、黒字化して、株価が何倍にもなる場合があります。しかし、会社がつぶれる可能性も高いわけです。そのため、ギャンブル要素が高くなることもあり、オススメは出来ません。
以上のようなこともあり、資金1万円以下でも株式投資は始められますが、やめておいた方が良いでしょう。
株の選択肢が少なすぎます。
資金が少なすぎては、増やしたときにそれほど増えた気がしない
さて、1万円の資金では株の選択肢が少なすぎるわけですが、10万円ならそれなりに銘柄数があることがわかりました。
しかし、「10万円の資金でも少ない」と言えます。
なぜなら、10万の資金では、増やしてもそれほど増えた気がしないからです。
例えば、10万円を10倍に増やしても、100万円にしかなりません。しかし、30万円を10倍に増やせば300万円になります。50万円を10倍に増やせば500万円になります。増やした時のこの差は大きいわけです。
そこから、さらに10倍に増やしたときに、元手10万円は1,000万円になります。しかし、元手50万円の場合は5,000万円になります。同じ増やし方で増やした後に、残ったお金が1,000万円と5,000万円では、この差は大きいと感じるのではないでしょうか?
このように、株式投資の資金として1万円は論外ですが、10万円でも少し心もとないというわけです。
増やした時のことも考えて、株の元手を考えるといいでしょう。あなたは株でいくらまで資産を増やしたいのでしょうか?
株式投資は余裕資金で行うべし!!
あなたの投資資金を決めるのに、とても重要なことがあります。それは、『株式投資の資金は余裕資金の範囲内』にすることです。余裕資金とは、無くなっても良い位の現金と考えてください。その位の元手から始めるのが良いでしょう。
重要:株式投資は余裕資金で行うべし!!
なぜなら、投資に絶対はないからです。上がると思っている株価が一向に上がらずに、下がり続けることもあるのです。
例えば、ITバブル期に『インターネット総合研究所』という銘柄がありました。今も会社自体は残っておりますが・・・。(汗)
その、インターネット総合研究所は、1999年12月22日に東証マザーズ(市場の名前)に上場しました。
IT株として期待されたこの銘柄は、なんと、公募価格は1株『1,170万円』でした!!
そして、初値(取引された最初の値段)は、5,300万円だったのです!!そこから、年をまたいで翌年まで上がり続けて、最高値(一番高い値段)は、7,742万円を付けたのでした。
それだけ、期待された銘柄でしたが、なんと、この時がピークで、そこから株価は下がり続けました。
そしてついに、2007年には上場廃止になりました。株式上場から10年ももたずに、市場から退場することになったのです。
株価は1株10,000円以下にまでなりました。
このように、期待されていた株も、上がらないことがあるわけです。
もしも上がると思っていた株が上がらない場合、あなたが用意した資金が無くなってしまうこともあります。そのようになった場合でも、困ることのないように、株式投資は余裕資金で行うことが、鉄則です!!
株の元手はいくらにしたら良いのか?
筆者は、株の初心者が始める資金としては、『30〜50万円』が適当ではないかと考えます。
30〜50万円であれば、もし無くなったとしても、ほとんどの人が1、2ヶ月がんばって働けば稼ぐことのできるお金ですし、このくらいの資金であれば、株で増やしたときにそれなりに増えます。
先述のとおり、元手30〜50万円を10倍に増やした時に、10万円ではやっと100万円になりますが、30万円は300万円になりますし、50万円は500万円になります。
増やした時に100万円と300〜500万円の、この差は大きいと感じるはずです。
私の経験談としては、資金50万円を2,000万円まで増やしました。もし、この時の元手が10万円だったとしたら、利益率から考えると、400万円までしか増えなかったことになります。株で資金が増えたときに400万円と2,000万円では、えらい違いです。
このような経験もあり、株の初心者が始める資金としては、無理のない余裕資金の中から30〜50万円で初めてみるのが妥当ではないかと考える理由になります。
もちろん、余裕資金が10万円程しかない場合は、10万円から始めてみてもよろしいかと思います。
月々に少しづつでも貯めて、10万円の資金で株を長期保有しつつ、ある程度自分で増やして、自信がついた時に資金を追加するのも良いでしょう。
例えば、月々1万円を貯金して、1年後に貯まった12万円のうちの10万円を追加する。というような感じです。
このように、無理のない資金計画をたてて、株式投資の資金に充てると良いでしょう。
『株式投資はいくらから始めれば良いのか』は、以下の記事も参考にしてください。
株式投資はいくらから始めれば良いのか?
株式投資に必要な知識を知る
冒頭でお伝えしたとおり、株式投資に『必要な知識』をお伝えします。それは、次の6つになります。
・投資する株(銘柄)を探す方法
・株(銘柄)の分析方法
・取引のルールを覚える
・資金管理をする
・税金について知る
これらの6つをすぐに全て覚える必要はありません。実際に行動しながら少しづつ覚えていきましょう。
STEP1では、『株の仕組み』についてだけ解説します。
株式投資(株式会社)で利益を得る仕組み
まずは、株の仕組みを簡単に説明します。
あなたは、株を買うことで株式会社に出資します。出資することでその会社の株主になります。出資された会社は、そのお金を使って会社を発展させます。発展させた会社に利益が出ると、その利益の一部をお礼として、配当金や株主優待の形で株主に還元します。さらに将来、会社の株が上がることで、株の値上がり益をあなたにもたらします。
この、株主に対する配当金のことを『インカムゲイン』と言います。一方、将来の株の値上りにより利益を得ることを、『キャピタルゲイン』と言います。
これが基本的な、株式投資で利益を得る仕組みになります。
また、配当金は、株主の権利の1つです。このような株主の権利は主に3つあり、株主としての義務が1つあります。次は、その株主の権利と義務についてお伝えします。
株主の権利と義務
先述のとおり、株を保有すると株主になります。株主になると主に3つの権利が与えられます。また、1つの義務が生じます。
株主の権利の1つ目は、先ほどお伝えした配当金を受け取る権利です。正式には『利益配当請求権』と言う権利になります。
株主の3つの権利と、1つの義務は、次のとおりになります。
2.株主総会での議決権
3.残余財産の分配を受け取る権利
まずは3つの権利について説明します。
1.配当金を得る権利(利益配当請求権)
配当金を受け取る権利が株主にはあります。しかし、上場企業の全ての会社が配当金を出している訳ではありません。上場企業約4,000社のうち、約3,200社が配当金を出しています。
つまり、配当金を出している会社の株主になれば、配当金を受け取れるわけです。配当金を受け取るには配当権利日という、株主の権利が与えられる日が会社ごとに設定されています。その日に株を保有していると、その会社の株主の権利が与えられることになります。
2.株主総会での議決権
次の権利は議決権です。株主になると株主総会での議決権が与えられます。会社の議案に対して、あなたの持ち株分の賛成票や反対票を入れられるわけです。
株を51%以上持つと、会社の議案に対して多数派になります。そのため、会社に対しての意見が必ず通ることになります。会社で一番株を持っている人を筆頭株主と言います。
3.残余財産の分配を受け取る権利
会社を清算すること(つぶれること)になった場合、会社に残った財産を、受け取る権利があります。これを『残余財産分配請求権』と言います。あなたが株を保有している割合に応じて、会社に残っている財産があなたに分配されます。
株主の義務
株主には権利に対して、義務があります。それは、『株式の引受価格を限度とした出資義務』と言います。
これは、あなたが出資した額は株価が下がることで、損をすることがありますが、あなたが出資した額以上に責任を負う必要はありません。という意味です。
例えば、あなたが50万円分会社の株を買って保有していたとします。
その会社が、50億円もの負債を抱えて、倒産してしまいました。その場合でも、あなたは出資した分の50万円は無くなることがあっても、それ以上に損をすることはありません。
これは、裏を返せば、出資した額以上は損をしないけど、出資した額が返って来なくても、文句は言えないよ。ということになります。
つまり、『株式投資は自己責任』で行わなければならないわけです。
そのため、特に株の長期投資では、銘柄を慎重に選ぶ必要がありますね。
株の仕組みを理解することは大事です
先述のような、株の仕組みは覚えなくても株の売買は出来ますし、利益をあげることは出来ます。しかし、株の仕組みを知らないで株の売買をすることは、株の値動きを追うだけのことになりがちです。
値動きを追うだけになってしまうと、会社の本来の価値を見失ってしまい、思いがけないときに株を手放すことにつながります。
例えば、株価は、上がる時も下がる時も行き過ぎた株価になってしまうことがあります。会社の業績の何倍も上がったり、逆に会社の業績は良いのに株価は低迷している様な状態になるわけです。
このようなときに、株の値動きを追うだけになってしまうと、それは、株の高値掴みや大底での売却につながることもしばしばあります。そこで、株の仕組みを理解していると、落ち着いて対処できることがあるわけです。
上記のような株を売るときに失敗しないためにも、株の仕組みを覚えることは株の本質をつかむことになり大事なことと言えます。
株の本質とは、株を通じて会社を応援したり、あなたの議決権を行使したりすることで、会社に意見を反映させて、会社を成長させることです。
会社を応援ししつつ、成長をさせ、結果、あなたに利益をもたらすことが、株の本質であり長期投資の醍醐味なのです。
さて、STEP1では、『株の仕組み』をお伝えしました。ここでは簡単に覚える程度で大丈夫です。株の分析手法などの詳しい内容は、STEP3の『株の銘柄の選び方』でお伝えします。
少しづつ、着実にステップアップしていきましょう!
STEP1は、以上で終了になります。
お疲れさまでした!
最後にまとめで、復習をしましょう。
まとめ(STEP1の復習)
STEP1では、株式投資に必要なものとして、『証券口座』と『投資資金(元手)』について、お伝えしました。
証券会社選びに迷ったら、おススメの証券会社の中から選んでください。
株の長期投資では、日本株に投資する限り、どこの証券会社に口座開設しても、それほど変わりません。
そのため、手数料が出来るだけ安い証券会社や、長期投資に役立つ投資ツールが揃っていれば、特に問題はないといえます。
これが、アメリカ株で長期投資をしたいというのであれば、証券会社は限られます。なぜなら、アメリカ株を扱っている証券会社は、まだまだ数少ないからです。
しかし、日本株であれば、どこの証券会社でも買えるので、まずは安心して口座開設をしてみましょう。
口座を開設するときに、口座の種類を選びます。
口座の種類はいくつかあり、株式投資の初心者におススメな口座の種類は『特定口座の源泉徴収あり』になります。
特定口座であれば、面倒な株の『年間取引報告書』を自分で作成する必要がありません。また、源泉徴収ありならば、面倒な税金も証券会社が自動的に利益から天引きしてくれます。
このように、面倒な作業はすべて証券会社がやってくれるため、『特定口座の源泉徴収あり』の口座は初心者にはおススメです。
次に投資資金についてです。
株式投資初心者には30~50万円の投資資金で始めることが妥当だと考えます。
それは、30~50万円なら、株で損をして全てが無くなったとしても、ほとんどの人が1,2ヵ月がんばれば稼げる額であり、また、そこから増やした時に、それなりに増えるため、その差は大きいわけです。
もちろん、株式投資は余裕資金でやるという、鉄則も忘れてはいけません!!
さて、ここまでで、あなたは口座開設をする証券会社を決めて、株で長期投資をするための資金額を決めているはずです。
STEP2では、実際の『証券口座の開き方』と『口座への入金の仕方』をお伝えします。
STEP2へお進みください。⇒ 『STEP2 [〜3日目]証券口座を開設して入金する』